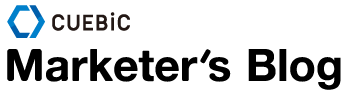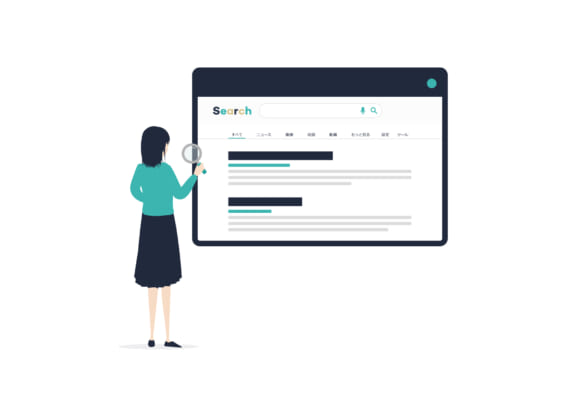SEOライティングとは?SEOの基本とコンテンツの作り方

SEOライティングとは、SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)を意識した記事の執筆方法を指します。 SEOライティングの基礎知識や具体的な書き方、作成したコンテンツを検索エンジンにも正確に理解してもらうためのHTMLマークアップ方法をご紹介します。
【積極採用中】 株式会社キュービックでは、デジタルメディア事業を一緒に推進する仲間を募集しています。
受賞歴 ・4年連続「働きがいのある会社」(毎年約60カ国で7,000社参加)ベストカンパニー選出 ・2020年 ホワイト企業アワード受賞
目次
SEOライティングとは
SEOライティングは、ユーザーの検索ニーズを満たすと同時に、Googleの検索エンジンにも評価されることを目的としています。
一般的なメディアは、ニュースバリューやジャーナリズムといった「発信者が考えていること・伝えたいこと」を主軸にしていますが、SEOライティングは「受け取り手が知りたいこと」を完全に満たし、適切に届けることを主軸に構成されている点に大きな違いがあります。
「SEO効果のあるコンテンツ」とは?

検索ユーザーに対して、価値の高い検索結果を提供することを目的として、Googleは検索品質の評価者向けに「検索品質評価ガイドライン」を一般公開しています。
検索品質評価のガイドラインは、大きく分けて3つで構成されており、「ページ品質(Page Quality)」、「モバイルユーザーのニーズ」、「ニーズメット(Needs Met)」が検索品質に影響するとしています。その中で重要視しているのは、検索品質評価ガイドラインでも頻繁に登場する「E-A-T」と「YMYL」という概念です。
こうした複数からなるGoogleの検索基準を満たし、ユーザーのニーズに十分に応えることが、「SEOに効果があるコンテンツ」の絶対条件となるでしょう。
ページ品質(Page Quality)
ページ品質(Page Quality)とは、「コンテンツの品質が高く、信頼できるかどうか」を判断するGoogleの品質基準。
Needs Met同様に、評価は5段階に分けられており、「コンテンツの適切な質と量」「プロフィールや問い合わせ先などのサイト情報」「専門家からの被リンクやユーザーレビューなどの評判」などから判断されています。
モバイルユーザーのニーズ
モバイル(スマートフォン)は、PCに比べて“移動中”や“外出先”など利用シーンは多岐にわたります。また、アプリ起動や通話などの多様な機能がある一方で、画面が小さくタイピングや画面操作が難しいため、例えば「東京 レストラン」と検索する場合、「近くにあるレストランを知りたい」だけでなく、「道順を知りたい」「オンライン予約を行いたい」など、複数のニーズが含まれるケースもあります。
Googleは、こうしたモバイルユーザーのニーズを想定し、適切なコンテンツを表示することが重要としています。
ニーズメット(Needs Met)
Needs Metとは、「検索結果が、モバイルユーザーのニーズを満たしているか」という評価基準を指します。
Googleは、ページの作成者が適切にモバイルユーザーのニーズを理解し、検索したユーザーに対して満足度の高いページを提供しているかどうかを判断しています。最高評価のFully Meets(FullyM)から、最低評価のFails to Meet(FailsM)まで、Needs Metの評価基準は5段階に分けられています。
E-A-T
E-A-Tとは、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の略で、Googleが「品質の高いページである」と評価する観点のひとつです。
Expertise(専門性)とは、扱っているテーマに対してコンテンツの作成者が専門性を備えていること、Authoritativeness(権威性)とは、扱っているテーマにおいてコンテンツ作成者が認められており権威性があること、Trustworthiness(信頼性)とは、信頼できるWebサイトやコンテンツであることであり、これら3つがSEOライティングに求められています。
YMYL
YMYL(Your Money or Your Life)とは、お金や健康など、人生や生活に大きく影響するジャンルを指します。
例えば、身体に痛みや不調を感じて検索した場合に、誤ったコンテンツが検索結果に表示されていると、ユーザーの健康を損なう恐れがあります。コンテンツの品質が人生や生活に影響する可能性のあるYMYLに関するジャンルに対しては、Googleは「より厳しい評価基準を設定する」としています。
■YMYLジャンル<例>
- ニュースや時事問題に関する情報(News and current events)
- 法律や公的サービスに関する情報(Civics, government, and law)
- 投資や保険などお金に関する情報(Finance)
- オンラインでの買い物や支払いに関する情報(Shopping)
- 健康や安全に関する情報(Health and safety)
- 人種や国籍、年齢など人の属性に関する情報(Groups of people)
SEOライティングで大切にしたいこと
前述したGoogleの検索品質評価ガイドラインは、150ページにも及ぶボリュームで品質評価についての説明がありますが、結局のところ、「ユーザーが抱える課題の解決に向き合い、ニーズを満たすコンテンツを提供する」ということがSEOライティングでは最も重要だということになります。
検索エンジンは今や人々の生活に欠かせない存在となっており、電気やガス、水道と同じように、社会や生活のインフラともいえるでしょう。間違った情報を掲載してしまうことは、コンテンツを読んで意思決定やアクションを起こしたユーザーの人生を変えてしまったり、良くない影響を及ぼしたりする可能性があるからです。
そのため、SEOライティングには「Googleのアルゴリズムをハックする」という企図ではなく、ユーザーが知りたいことにとことん向き合い、品質の高いコンテンツを提供する真摯な姿勢が求められます。質の高いコンテンツを提供することは、結果的にGoogleにも評価され、検索結果にも反映されるものになるといえるのです。
キュービックの6つの品質基準

では、「品質の高いコンテンツ」とはどのようなものを指すのでしょうか。作成者の認識を合わせるために、キュービックでは6つの基準を設けています。
1.網羅性
ユーザーが十分に納得できる情報になっているか、対策したいキーワードに直接関係することだけでなく、関連の情報まで網羅されているかどうか。
2.一貫性
タイトル、アイキャッチ、ディスクリプション、本文などが一貫しているか、読んでいて文脈に違和感がないか。
3.助動性
コンテンツを読んだユーザーの課題を解決するためのアクションに対して、きちんと後押しができているか。もちろん強引に誘導するのではなく、あくまで行動のキッカケや後押しまでとしています。
4.信頼性
信頼性は6つの中で最も重要な指標とされており、コンテンツの内容が専門家の意見や定量的なデータなどで裏付けが取れており、公正中立な情報であること。
5.可読性
ユーザーニーズを満たすために、読みやすさも大切にすること。専門用語の多用や冗長な文章では、適切に情報を伝えることができないからです。
6.独自性
1~5の基準を満たしたうえで、独自性が重要になると考えています。ただし、どの記事にも独自性が求められるというわけではなく、ユーザーの読みやすさや納得感を高めるために切り口を工夫するケースもある、としています。
【積極採用中】 株式会社キュービックでは、デジタルメディア事業を一緒に推進する仲間を募集しています。
受賞歴 ・4年連続「働きがいのある会社」(毎年約60カ国で7,000社参加)ベストカンパニー選出 ・2020年 ホワイト企業アワード受賞
SEOライティングの具体的な方法

キュービックの記事制作プロセスは、「ニーズ調査」を行ったうえで、「企画(構成案)」を作成し、構成案をもとに「ライティング」を行う、という流れで進めています。具体的な方法を解説します。
ニーズ調査
ニーズ調査は、「定量調査」と「定性調査」の2つがあります。どちらも、ユーザーのニーズを正しく捉え、品質の高いコンテンツ作りのために必要なプロセスです。
定量調査
定量で検索ニーズを調査するために、Googleの「サジェスト(検索補助)」機能を活用します。サジェストとは、検索ボックスにキーワードを入れると表示される、過去の検索データをもとにした、検索ユーザーの補助のためにGoogleが提供している機能です。
キュービックでは、ツールを使ってサジェストを洗い出しています。例えば「ウォーターサーバー」であれば、「ウォーターサーバー 一人暮らし」「ウォーターサーバー 安い」など、数多くのサジェストが抽出されます。こうした関連のキーワードを確認し、ユーザーがどのようなことを知りたいのかを量るのが定量調査です。
定性調査
定性調査は、ターゲットや専門家などに対して、具体的にどのようなことに困っているのか、検索するきっかけは何かを、インタビューなどを通じて把握する調査です。例えば、「20代の転職」というコンテンツを作成する場合は、20代で転職を検討している人に対して、「なぜ転職しようと考えたのか」「転職活動中に困ったことは」などのニーズを確認します。
また、ニーズを満たすコンテンツにするためには、解決策や専門的なアドバイスが必要です。20代の転職を支援している転職エージェントなどにインタビューを行い、「20代の転職では何がポイントになるのか」「どのようなことを大切にすればいいのか」を聞いて、企画(構成案)に活かします。
ペルソナ(ターゲット)設定
定量、定性調査から見えてきたニーズをもとに、具体的にペルソナ(ターゲット)を設定します。
ペルソナは、検索ユーザーが検索に至った背景や、知りたい解決策などを調査結果から類推して設定しますが、キーワードの粒度によってペルソナは変わります。
例えば「ウォーターサーバー」のように抽象度が高いキーワードの場合、「一人暮らし向けのウォーターサーバー」「オシャレなウォーターサーバー」など、さまざまなニーズが存在するため、詳細なペルソナを設定することができません。一方で、「ウォーターサーバー 一人暮らし 失敗例」など、対策キーワードが具体的であるほど、ペルソナを設定しやすくなるでしょう。
また、ペルソナの設定は、キーワードによっては具体的なシーンまでイメージしなければ、ニーズを正しく満たした企画(構成案)にならないケースもあります。
例えば、期日までに支払いがないと送付される「督促状」のようなキーワードでは、文字だけで「督促状について調べている=督促状について知りたいのだ」と捉えてしまうと、「督促状とは」「どのような場合に送付されるのか」で始まるコンテンツになってしまいます。
しかし実際にはこのキーワードを検索している段階で、おそらく検索ユーザーの手元には督促状が届いており、検索して解決策を探しているという状況が推測できます。手元に督促状が届いている状態であれば、督促状の意味を長々と説明するよりも、「督促状が届いた際の解決策」をわかりやすく提示するようなコンテンツが適切であるといえるでしょう。
このように、ペルソナ設定をする際は、定量・定性の調査結果から検索ユーザーの属性や知りたいこと、検索に至った背景をイメージすることが重要です。
ゴール設定
SEOライティングでは、「『検索する前』と『読んだ後』でユーザーの気持ちや行動がどのように変化するのか(ゴール)」を事前に設定します。
ユーザーは検索して得られた情報でニーズが満たされなかった場合に、再度検索行動を起こすことになります。前述したGoogleのNeeds Metのうち、最高評価の「Fully Meets」は、「コンテンツに満足し、他の検索結果を必要としない」状態を指しています。知りたかった情報が得られている状態をイメージして、コンテンツのゴールを設定しましょう。
企画(構成案)作成
定量調査で洗い出した関連キーワードの一覧を見ながら、類似したキーワードを分類して構造化していきます。
例えば「転職エージェント」であれば、関連キーワードの「転職エージェント キャリアアドバイザー」や「転職エージェント キャリアアドバイザー 相談」は「キャリアアドバイザー」でカテゴライズします。
他にも、「転職エージェント 求人」「転職エージェント 求人 特徴」などは「求人」にカテゴライズするなどしてまとめていくと、ユーザーの知りたいことがツリー状に構造化されます。構造化することで、ユーザーにわかりやすいコンテンツになると同時に、Googleに対しても構造が伝わりやすくなります。
分類したカテゴリごとに見出しを立てて、企画(構成案)を作成します。見出しの数に目安はありませんが、正しく構造化されているかどうかがとても重要です。
正しい構造化例

誤った構造化例

ライティング
キュービックでは「新聞や雑誌など紙のコンテンツと比べて、ユーザーはWebのコンテンツを読まない」ことを大前提としています。
紙のコンテンツは手に取った時点で「読む」という意思決定をして、「読もう」と思ってページを開いています。一方、Webのコンテンツは、ユーザーが抱える課題の解決策を知りたいだけなので、「読もう」という姿勢で検索しているわけではありません。
そのため、紙のコンテンツであれば必要のない「読む気のないユーザーに読んでもらう工夫」や「読んでいてつらいと思われないようにする配慮」が求められます。これはSEOライティングの大前提の考え方です。
ただし「E-A-T」や「6つの品質基準」の項目でご説明しているとおり、専門性や網羅性もコンテンツの品質向上のためにとても重要です。専門性や網羅性を高めるために文章が長くなると、読むのが大変になる。こうした相反する課題に対して、構造化が有効に働きます。
例えば、目次を見るだけで流れがわかるようになっていれば、全文を読まなくても目次のリンクから知りたい箇所に遷移することができます。また、本文が推測できる見出しにすることで、目次で概要を理解することができるでしょう。
もちろん本文も、最後まで読まないと結論がわからない文章では、読み手のハードルが上がってしまいます。
SEOライティングでは、まず「結論(主張)」を先に言う。そして「理由(根拠)」を伝えるといった文章の組み立て方にすることで、わかりやすいコンテンツになります。特に、YMYLのジャンルは客観的な根拠が重要です。SEOライティングでは、必ず結論(主張)と理由(根拠)をセットで伝えましょう。
コンテンツを正しくHTMLマークアップする

Webページは、HTMLという言語で記述されています。HTMLで正しくマークアップすることによって、ユーザーにとって読みやすいコンテンツになるとともに、検索エンジンにもページの内容を正しく伝えることができます。
HTMLマークアップが正しく設定されていないと、せっかく良いコンテンツを作ったとしても検索エンジンに評価してもらえない可能性があります。SEOに最適化するための、代表的なHTML要素をご紹介します。
タイトルタグ(titleタグ)
タイトルタグとは、ページのタイトルを示すタグです。
タイトルタグが検索結果に表示されることが多いため、ユーザーが検索結果を見たときに、ニーズに応えていることが伝わるようなタイトルを付けます。なお、さまざまなキーワードを盛り込もうとして、極端に長いタイトルや、不要なキーワードを乱用することは避けましょう。

説明文(meta description)
meta descriptionはページの概要を示すタグです。
検索エンジンにページ内容を伝えるため、meta descriptionにはコンテンツの要約文を入れます。 meta descriptionは検索結果に表示される可能性があるため、説明文がきちんと表示される程度の長さで作成しましょう。

見出しタグ(hタグ)
大見出し、中見出し、小見出しに対して、hタグを設定します。見出しタグは、検索エンジンに構造を伝える重要な設定。構造自体が適切でないと、検索エンジンから正しく評価されない可能性があります。
HTMLマークアップの前に、適切な構造になっているかをしっかりと確認しておきましょう。

alt属性
alt属性は、画像の代替テキストを指します。検索エンジンは画像の内容を人間のように認識することができないので、alt属性のテキストを画像認識のための情報のひとつにしています。
また、画像を表示しないテキストブラウザや、音声読み上げソフト(スクリーンリーダー)を利用している場合、画像のalt属性に記載された内容が表示、または読み上げられます。そのため、端的に画像を説明するテキストをalt属性に記述する必要があります。

まとめ
SEOライティングは、検索キーワードに込められたユーザーのニーズを正しく捉えることが大切です。捉えたニーズをもとに構成案を作成しライティングを行うため、基礎となるニーズ把握が誤っていると、構成案やコンテンツもニーズから逸れた内容になってしまいます。
検索ユーザーの状況や課題を具体的にイメージし、納得できる解決策を提示する、信頼性の高いコンテンツ作りを目指しましょう。
【積極採用中】 株式会社キュービックでは、デジタルメディア事業を一緒に推進する仲間を募集しています。
Webマーケター(広告運用、コンテンツSEO)職 エディター職
受賞歴 ・4年連続「働きがいのある会社」(毎年約60カ国で7,000社参加)ベストカンパニー選出 ・2020年 ホワイト企業アワード受賞