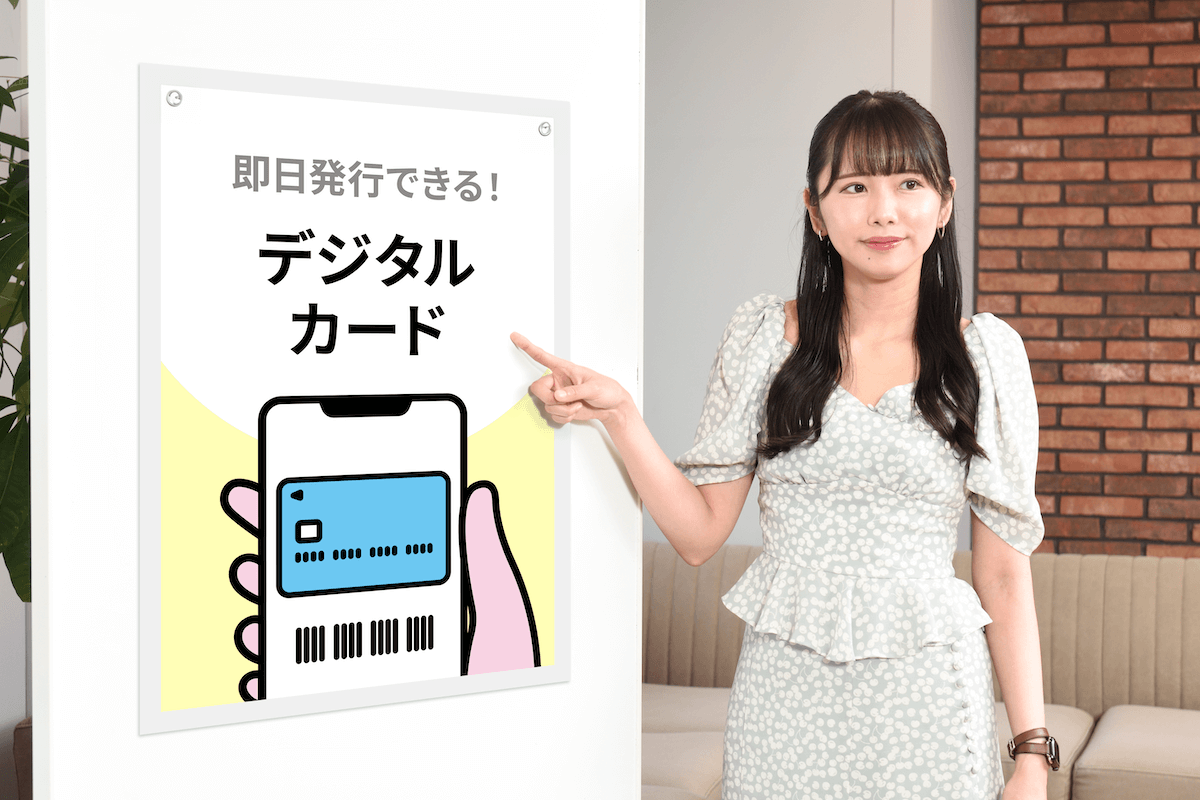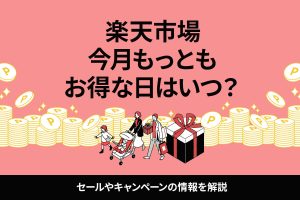KITCHEN
家庭用冷凍庫の選び方!用途に合った容量や省エネ性能をプロが解説

冷凍食品の保存に便利な冷凍庫。食品のまとめ買いやお取り寄せなどを利用する人が増えたことに伴い、サブ用として使える「セカンド冷凍庫」の需要が高まっています。しかし容量はもちろん、冷却方式や扉の向き、省エネ性能などに違いがあり、どれを選べばよいか迷ってしまいますよね。
この記事では、家電プロレビュアーの石井和美さんに、冷凍庫の基礎知識と選び方を教えてもらいました。保存したい食品の種類や用途に合わせて、使いやすい冷凍庫を選ぶポイントを解説しているのでぜひ参考にしてください。
▼おすすめ商品を知りたい方はこちら


家電プロレビュアー
石井和美さん
白物家電や日用品を中心とした製品レビューを得意とする家電プロレビュアー。忖度(そんたく)のない率直なレビューが人気で、Webや雑誌、ラジオ、テレビなどで幅広く活動。2018年、茨城県守谷市に家電をレビューするための一軒家「家電ラボ」を開設。冷蔵庫や洗濯機など大型家電のテストも行っている。
本記事は、提携する企業のプロモーション情報が含まれます。掲載するサービス及び掲載位置に広告収益が影響を与える可能性はありますが、サービスの評価や内容などはyour SELECT.が独自に記載しています。(詳しくはAbout Usへ)
目次
選ぶ前に知っておきたい冷凍庫の基礎知識
はじめに、サブ用の冷凍庫をもつメリットやデメリット、冷却方式やドアの開閉方式の違い、電気代のことなど、冷凍庫の基礎知識について石井さんに伺いました。
サブ用の冷凍庫をもつメリット・デメリット
サブ用の冷凍庫をもつことのもっとも大きなメリットは、なんといっても食品などを冷凍保存するスペースが大きく増えることです。買いだめをして買い物に行く頻度を減らしたり、冷蔵庫に入りきらないおかずの作り置きができたりします。また、ふるさと納税の返礼品やお取り寄せ食品などを保存するスペースを確保することができます。
一方デメリットは、設置スペースの確保が必要なことや、電気代がかかってしまうこと。本体は小型なサイズが多いですが、冷蔵庫と同等の電気代がかかるケースもあるため注意が必要です。

サブ用の冷凍庫があると、食品の買いだめやおかずの作り置きなどもしやすくなる
冷却方式の種類
冷凍庫の冷却方式は、「直冷式」と「ファン式(間冷式)」の2種類に分けられます。
直冷式は庫内に設置されている冷却器で内部を冷やす方式。ファン式は、庫外に冷却器が設置されており、ファンで冷気をまんべんなく循環させるため、食品が均一に冷やせます。
それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。
| 冷却方式 | 直冷式 | ファン式 |
|---|---|---|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
冷却効率のよい直冷式は電気代が安い傾向にあるものの、容量や収納する量、使い方によって消費電力は大きく左右されます。最近は省エネ性能に優れたファン式のモデルもあるので、霜取り不要のファン式が主流になっています。

直冷式は霜が巨大化することで冷却効率が悪くなるため、定期的に霜取りをする必要がある
ドアの開閉方式
ドアの開閉方式には、おもに「上開き(チェスト型)」と「前開き」の2タイプがあります。
| 開閉方式 | 上開き | 前開き |
|---|---|---|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
上開き式は、上部にドアを設計したタイプ。大きな食品も収納しやすく、冷気の漏れが少ないのが利点です。
前開き式は、上開き式に比べると冷気が漏れやすい傾向にあるものの、収納ケースを引き出しにすることで、冷気の漏れを抑えた商品もあります。
家庭用で人気を集めているのは、縦長の前開きタイプで、中身の整理整頓がしやすく冷気が逃げにくい構造の引き出し式です。

上開きタイプ、前開きタイプそれぞれの一例。使い勝手は大きく変わる
冷凍庫の電気代
先述したように、サブの冷凍庫を購入すると追加で電気代がかかります。
おおよその年間電気代は、年間消費電力(kWh)×1kWhあたりの電気料金単価(円/kWh)という計算方式で算出できます。
例えば、年間消費電力が300kWh、1kWあたりの電気料金単価が27円の場合、年間の電気代は約8100円、一ヶ月あたりの電気代は約675円になります。
年間消費電力の一例を、以下にまとめました。
電気代の目安(電気料金単価1kWあたり27円の場合)
| 年間消費電力 | 一ヶ月あたりの電気代 | 年間の電気代(2022年9月試算) |
|---|---|---|
| 300kWh | 約675円 | 約8100円 |
| 350kWh | 約788円 | 約9450円 |
| 400kWh | 約900円 | 約1万800円 |
| 450kWh | 約1013円 | 約1万2150円 |
ただし上記はあくまで目安で、本体のサイズや性能、使い方によっても電気代は変動します。
1kWhあたりの電気料金単価は電力会社や料金プランごとに異なるため、自宅に届く検針票や、電力会社のWebサイトなどで確認してください。
また、省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)に基づいて設定されている「省エネ基準達成率」が100%以上のモデルを選ぶのもよいでしょう。
家電のプロが教える冷凍庫の選び方
用途に合わせて使いやすい冷凍庫を選ぶためのポイントを、石井さんに教えていただきました。
保存する食品で選ぶ
扉の開閉方式によって、保存に適した食品や使いやすさが異なります。食品の種類に合った冷凍庫を選びましょう。
大きな冷凍食品を保存したい人|上開きの冷凍庫がおすすめ
上開きの冷凍庫は、食品を小分けする必要なくそのまま保存できるため、コストコなどで調達した大きめのピザやパン、ブロック肉のほか、釣った魚などを丸々一匹入れて保存したい場合などにおすすめです。扉の開閉時の冷気の漏れも少ないので、食材の鮮度もより長期間保つことができます。
ただし、家庭用の冷凍庫は前開きの商品が主流で、上開きのものは大容量のモデルになりがちです。上開きを選ぶ際は、必要な容量だけでなく設置スペースもしっかりと検討してください。

大量購入した食品や大きなものを冷凍保存するなら、上開きが便利
一般的な冷凍食品や、小分けした食品を冷凍保存したい人|前開きの冷凍庫がおすすめ
前開きの冷凍庫は、お弁当や料理に使う一般的な大きさの冷凍食品や、作り置きのおかず、アイスクリームなどの保存に向いています。特に引き出し式は整理がしやすく、収納場所も特定しやすいため、すばやい出し入れが可能です。

引き出し式の冷凍庫は、奥に入れた食品が取り出しやすく、管理も楽
耐熱天板のものを選べば、上に電子レンジなどを置くことができるのも、メリットのひとつ。縦長でスリムな設計のモデルが多いのも魅力です。

スリムタイプの前開き冷凍庫なら、設置スペースを広く取れなくても置ける場合がある
容量で選ぶ
冷凍庫を選ぶ際に、特に検討が必要になるのが容量です。
100L程度の冷凍庫は、ふだん使用している冷蔵庫のサブ用として使うにはちょうどよいサイズ。買いだめしたい年末年始やふるさと納税の返礼品など、一時的に食品を保存したい場合にも重宝します。ただし、コストコのピザなどの大型食品は小分けして入れる必要があります。100L以上になると、かさばりやすい食パンや麺類、アイスクリーム、お弁当に使う冷凍食品など、入れられる食品の量や種類の幅も、大きく広がります。
150L以上の冷凍庫は、コストコで調達した大型食品も余裕で入る大きさ。サケなどの大きな魚を丸々一匹入れることも可能ですが、その場合は縦よりも横に広い上開き式がおすすめです。ただし、本体サイズが大きいので場所を取ります。
ちなみに、小型のものは直冷式のモデルもありますが、おすすめは霜取り不要のファン式です。必ず冷却方法もチェックして選びましょう。

「ほどよい容量で場所も取らない100L前後のモデルが売れ筋です」
温度調節機能にも注目
冷凍庫には、「温度調節機能」付きのモデルもあります。温度調整機能付きであれば冷却運転の強さを調整でき、例えば、夏季や食品が多いときは-22〜-24℃に、冬季や冷凍食品が少ないときは-16〜-18℃に設定するなど、食品の量や周囲の温度に応じて設定を変えられます。
中には、-24〜5℃と幅広い温度設定ができるものもあり、冷蔵に適した温度に切り替えられるため、冷蔵庫としても使用できます。冷凍食品を一時的に保存できないというデメリットはあるものの、必要に応じて使い分けられる点は便利です。

温度調節機能があると、そのときどきのニーズによって使い分けができる
冷凍庫の選び方|ポイントまとめ
冷凍庫は保存したい食品の種類や量、どんな風に使いたいかによって、扉の開閉方式や容量、温度調節機能をチェックして選びましょう。選び方のポイントをまとめました。
- 大きな食品を保存したいなら上開き式、小分けした食品を保存したいなら前開き式が使いやすい
- 容量はサブ用で日常使いするなら100L前後、大型食品を入れるなら150L以上が目安
- 冷却方法は霜取りが不要なファン式がおすすめ
- 冷蔵庫としても使いたいなら、温度調節機能付きのモデルを選ぶ
冷凍庫に関するよくある疑問Q&A
冷凍庫にまつわる疑問について、石井さんに教えていただきました。
Q. 肉や野菜の冷凍焼けを防ぐにはどうすればいい?
A. 冷凍焼けを防ぐコツは、食材のうま味成分や水分を閉じ込めて冷凍することです。機種は限られますが、食材を急速冷凍するような機能が付いたモデルを選ぶとよいでしょう。機能が付いていない場合は少し面倒ですが、冷蔵庫の急速冷凍機能を介して保存するという方法もあります。

「しっかりと密閉しないと、においが他の食材に移ってしまうこともあります」
Q. 冷凍庫内のにおい対策はどうしたらいい?
A. 食材を密閉して保存するのがにおいを出さないコツです。肉や魚、食パンも一つずつラップに包み、保存袋へ入れて空気を抜きながら密閉しましょう。そうすることで、においも冷凍焼けも防ぐことができます。
Q. 冷凍庫をベランダや庭などに置いても大丈夫?
A. 電気製品を風雨にさらされる屋外に置くのは危険です。水と電気の相性は非常に悪いため、コンセントが水に濡れることで漏電を起こす可能性があります。屋外用として販売されているもの以外は、必ず室内で使うようにしましょう。
Q. 霜取りはどのくらいの頻度でやればいい?
A. 冷凍庫の霜は、気になってきたらすぐに取り除くようにしましょう。放置すると霜はさらに大きくなり、冷却効率が落ちるだけでなく、庫内に食品を入れづらくなります。霜取りの手間を省きたい人は、冷却方式がファン式の機種を選ぶとよいでしょう。
Q. 冷凍庫の駆動音はどのくらい?
A. 冷凍庫は、一般的な冷蔵庫と比べると音が大きい傾向にあります。そのため、家族で会話をすることの多いリビングやテレビの近くには置かない方がよいでしょう。気になる人は、運転音を抑えた静音設計のモデルを選ぶのがおすすめです。

「サイズや機能から考えても、通常使用ならば家庭用で問題ありません」
Q. 家庭で業務用の冷凍庫は使える?
A. 使えますが、業務用はサイズが大きく本体の価格や電気代も高くなりがちです。業務用は家庭用の冷凍庫より低温の設定が可能なケースが多いため、食品の劣化防止と、長期保存が可能です。ただし、サブ用として使う場合は家庭用でも十分だと思います。
まとめ
- 冷凍庫は、霜取り作業が不要のファン式がおすすめ
- 電気代を抑えるには、省エネ基準達成率が100%以上のモデルが良い
- 扉はドアを上部に設置した「上開き式」と庫内全体が見渡せる「前開き式」がある
- 大型食品を保存するなら上開き式、小分けした食品なら前開き式の冷凍庫がおすすめ
- 冷凍庫をベランダなど屋外に置くのはNG
サブ用の冷凍庫は、保存したい食品に合わせて使いやすい形やサイズ、省エネ性能も意識して選ぶといいでしょう。この記事を参考にして、ニーズに合った冷凍庫を見つけてくださいね。
▼おすすめ商品を知りたい方はこちら

LATEST
このカテゴリーの最新記事